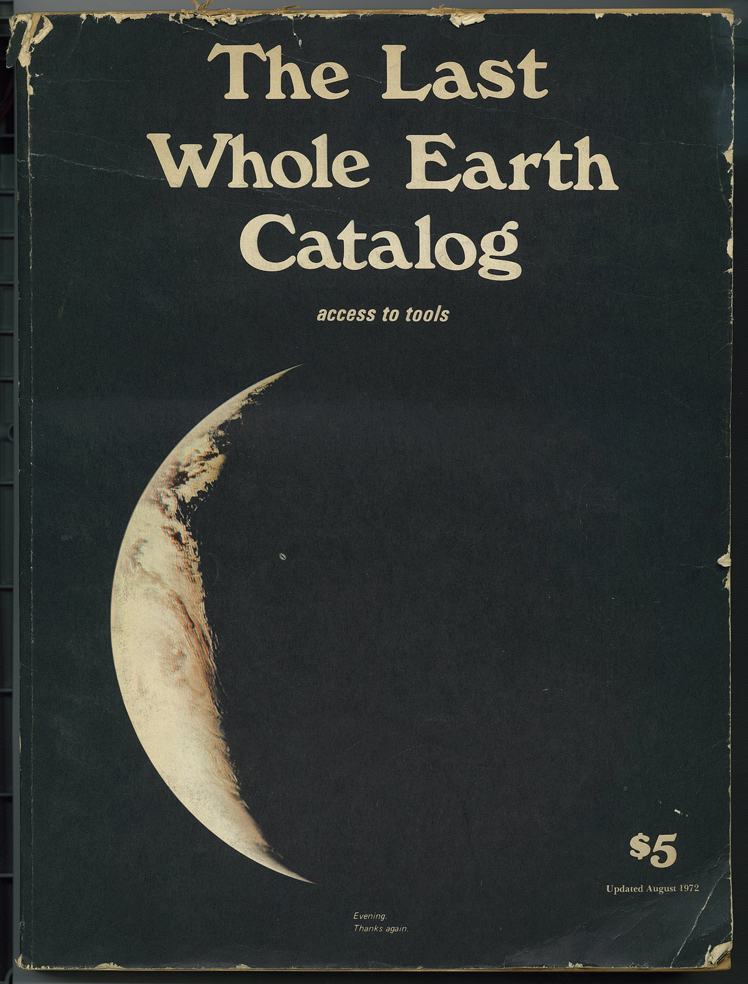ファッションブティックは、個人的な生活観、世界観への共鳴や賛同が購買を引き出すという、小売りにおいてそれまでになかった売る側と買う側の新しい関係をつくり出したことで画期的だったと言えます。そしてこのことは、個人的な世界観を表現するファッションデザイナーへの関心というもうひとつの動きへと広がっていきます。60年代後半から70年代は、世界を見ても日本を見ても新進気鋭のデザイナーが次々に登場してきたことで特筆される時代です。音楽や美術と同様に殻を破る個人的な美意識の表現はファッションにも及んで行き、80年代に入るとデザイナーブランドの時代をもたらすことになります。
ファッションデザイナーと言えば、それまではオートクチュールや高級プレタポルテなどの富裕層を顧客にするブランドをイメージしたものですが、登場してきた新しいデザイナーたちは、一般的な生活者が「買える値段の作品」を提供したところが画期的だったのです。こうしてファッション消費が活発になっていくのですが、その主役になったのが、当時、OLと呼ばれた女性たちです。給料の絶対額は低いのですが、親の家に同居している人が多く、家賃なし、食費などの生活費も親がかりで、いわゆる自由裁量所得が大きく、それが着るものや旅行に回っていったのです。この動きを後押ししたのが『アンアン』に始まり発刊ブームになった女性ファッション誌です。
話をもう一度ブティックに戻します。
ブティックはその世界観を表現するにふさわしい立地を求めて、立地の考え方に新しさをもたらします。商売にいいとされてきた人通りの多い繁華街や盛り場を敬遠し、発信する美意識を印象づけることのできる環境を求めていきます。そこで目を向けたのが都心の住宅地で、その発端になったのが原宿界隈だったのです。ランドマークになったのが表参道と明治通りの交差点にあったセントラルアパートで、ここにはクリエイターのオフィスが多く入居しており、そのことが発するイメージが世界観の表現を求めるブティックのオーナーを刺激したと言えます。また、セントラルアパートを中心に原宿は表参道へと発展していくのですが、そこでもうひとつランドマークになったのが同潤会アパートで、ここには独自の世界観を表現するブティックが詰まっており、興味や好奇心を刺激されたものです。
ちなみに、今、セントラルアパートは東急プラザ表参道原宿に、同潤会アパートは表参道ヒルズになり、同潤館という形でその一部を構成しています。
原宿・表参道界隈に端を発したこの動きは、東京では青山、代官山、自由が丘、吉祥寺の裏通り、小さな劇場の集まる下北沢へと広がっていきます。共通しているのはいずれも住宅地であること。また、街は裏道へと広がり、表の大通りよりも独自の世界観を発信する店と出会える期待感が膨らみます。これらの地域は今日、商業地としての評価を確立しているのですが、その発端になったのがブティックであることを見逃してはならないと思います。ブティックという業態は小売りにとどまらず、街づくりにも大きな影響を与えたとして記憶されるべきなのです。
このようにブティックが発端になってファッション市場の形成と発展が進んでいくのですが、これを強力に推進したのが若い女性をとらえるファッション専門店の台頭です。その御三家となったのが鈴屋、三愛、キャビンで、70年代には専門店の時代が到来します。確かコムデギャルソンを逸早く取り上げたのが鈴屋で、ここが展開していた銀座ベルブードワァの輝きは今も記憶に残っています。こうしてミージェネレーションである新世代はファッションを専門店で買い、百貨店は自分の母親、つまり旧世代が行くところという、ファッション購買における色分けが進んでいきます。ただ、そんななかで例外になったのが伊勢丹で、この店は新世代の支持を得て、ファッションに強い店として存在価値を築き上げていきます。
一方、70年代は専門店の台頭と歩調を合わせて新しい商業施設が都心部を中心に次々に開業していった時代でもあります。多くがファッションビルと呼ばれるもので、ファッション小売りの一大勢力になっていきます。代表的なものにパルコ(1969年)、黒川紀章設計の青山ベルコモンズ(1976年)、ラフォーレ原宿(1978年)などがあり、なかでも渋谷パルコ(1974年)は新しい街の開発の先駆事例になると同時に、若者の先端ファッションの発信地として画期的な役割を果たすことになります。ここには高い美意識を読み取れる着こなしの男女が集まってくることもあり、普通の生活者が楽しめる自己表現のひとつである「着こなし」の観察を仕事にしていたわたしは毎週末、出かけたものです。
というわけで、ブティックの登場はファッションビルという商業施設の開発にまで及んでいくことになるのです。
ところで、ファッション専門店の時代を切り拓いた御三家の繁盛はその後持続することなく、あるところは姿を消し、あるところは姿を変えることになります。要因はいろいろ考えられますが、最大の要因はミージェネレーションの次の新しい若者たち、つまりマテリアル世代をものにできなかったことです。ブランド志向するこの世代は、80年代にブランドの殿堂と化した百貨店に惹かれていったのです。ミージェネレーションに旧世代の店とされた百貨店が、次の世代の若者たちには「自分たちの店」として評価される。そしてその百貨店がさらにその下の世代であるロストジェネレーションの支持を得られず苦戦を強いられる。とても興味深いことで、新しく出てくる世代の若者をとらえ損なうとどうなるかを学び取ることができます。
この百貨店業態や専門店業態のその後については、機会を改めて考察することにします。
蔦川敬亮/禁無断転載